
「幻のヘビ」として、見つかるとたびたびニュースで話題になるシロマダラ。確かにシロマダラは見かけることが少ない珍しいヘビです。しかし実は、シロマダラは日本全国に生息し、場所によってはわりと身近にいるヘビであることは意外に知られていません。
本記事では、そんな「身近な珍生物・シロマダラ」に迫っていきたいと思います。
目次(クリックで各項目にとびます)
シロマダラの生息地
珍しいといわれるシロマダラですが、本州・四国・九州と北海道の一部と、日本全国的に分布しています。そして山間部から平地まで、あらゆる環境に生息しています。
それでもあまり見かけないのは、シロマダラは夜行性で、昼間は石の下・石垣の隙間・倒木の下やすき間・排水口のパイプの中・古い看板の裏…などに隠れており、なかなか人目につきづらいからです。また個体数自体も多くはありません。
その一方、自然度がさほど高くない宅地周辺の緑地や公園で見ることもあり、意外と宅地化に強い種でもあると感じます。
シロマダラの食べ物
シロマダラは爬虫類を専門に食べるヘビです。
日本本土に生息する、ヘビの食性をざっと挙げると
「アオダイショウ=ネズミ・鳥、ジムグリ=ネズミ・モグラ、ヤマカガシ=カエル・魚、ヒバカリ=カエル・魚・ミミズ、タカチホヘビ=ミミズ、シロマダラ=爬虫類、シマヘビ=様々な獲物、マムシ=様々な獲物」
…といった具合です。それぞれの種によって、食性が異なっているんですね。日本本土産ヘビ8種がうまく「餌によるすみわけ」をして、餌や生息環境の奪いあいにならないように進化しているのです。
シロマダラは、意外と宅地周辺の緑地でも見られると書きましたが、これは、宅地周辺でも棲息するヤモリや、トカゲ・カナヘビをエサとするためでしょう。逆にヘビの中では最も普通に見られるヤマカガシは、逆に田んぼなどの水辺が無くなり餌となるカエルなどがいなくなると、あっという間に見られなくなってしまいます。

ヘビを食べるシロマダラ
シロマダラは夜間にヤモリや、石垣などで隠れて寝ているトカゲを襲って食べるといわれています。しかし、もう一つシロマダラの重要な餌が「ヘビ」です。ヘビなのに他のヘビを食べるの?と驚く人もいるかもしれませんが、実は、ヘビにとってヘビをエサにすることは、合理的なことなのです。
ヘビは体が細いので、獲物を呑み込むのは大変です。しかしヘビの多くの種類はアゴを外して皮を思いきり伸ばして、自分の頭の何倍もある獲物を呑みます。しかし、ヘビの種類によって、皮がのび大きな獲物を呑み込むのが得意な種類と、あまり得意でない種類がいます。得意でない種類は、鱗の数が少ないため鱗と鱗の間の伸びる皮の部分が少なく、鱗が伸びないんですね。
ヘビの仲間が餌を食べる際、アゴをはずして良く伸びる皮を利用して大きな獲物を呑み込むのですが、ヘビの種類によって獲物を呑み込む能力に差があります。
たとえばアオダイショウは、体の鱗の数が多く鱗と鱗の間の皮が延びる部分も多いため、大きな餌を丸のみする能力が高いです。対してシロマダラは鱗の数が少なく皮がのびず、細めの獲物しか呑めません。アオダイショウはネズミや鳥などかさばる獲物を主食とするのに対し、シロマダラはトカゲなど細めの獲物を食べます。
そして、ヘビがヘビを獲物とする場合、獲物に手足が無く呑みやすく、そのくせ長い分質量はあり、一度の食事でたくさんの餌を摂取することができます。
隠蔽性の強いヘビにとって、食事回数が減ることは大きなメリットとなります。シロマダラは特に、小型で攻撃性の無いタカチホヘビをよく食べるようです。自分と同じくらいの長さのヘビを食べることもあります。

シロマダラは毒がある?
シロマダラには毒はありません。見慣れない独特の模様をしたヘビであり、人によっては毒ヘビに見えるようです。また瞳も縦長で凶悪な印象です。
気性は荒いので捕まえようとすると、身体を弓なりにして威嚇してきます。しかしシロマダラは全長は30㎝~70㎝の小型種で、人に害を与えるほどの力もなく、恐れる必要はありません。人から手を出さなければ、シロマダラ側から積極的に人間をかみつこうと襲ってくることはまずありません。マスコミが「ヘビ」というだけで大げさに恐ろしさを強調することがよくありますが、日本における毒ヘビ以外のヘビは恐れる必要は全くありません。また、シロマダラはつかむとかなり臭い液をかけてきます。人体への害は無いものの、あまり気分の良いものではないので一応気を付けましょう。
シロマダラを探すには
シロマダラを見つけやすい条件の一つとして「雨上がり」を狙うというのが、一つの有効な手段です。シロマダラは普段、夜間に石垣の間などでトカゲ・ヤモリの寝こみを襲ったりしているため人目につかないのですが、タカチホヘビを食べるためには雨上がりに出てきます。タカチホヘビは乾燥に弱いミミズ専門食のヘビで、雨天時によく出てくるからです。時期は、春から梅雨にかけてと、秋のはじめに見ることが多いです。
シロマダラがまったく生息していないところで闇雲に探しても効率が悪いので、生息地の目星をつけます。
第一の手がかりは、餌となるトカゲやヤモリがたくさんいる場所。私がシロマダラを見つけている場所の多くは、地域の中でもトカゲやヤモリが特に多い場所と感じます。歩くたびに数匹のトカゲ・カナヘビが出てくるような環境や、近くの公衆トイレにヤモリが大量に張り付いているような環境です。ただ、シロマダラの生息は局所的で、トカゲの住んでいる場所に必ずいるわけでもありません。
第二の手がかりは「シロマダラの死体」です。シロマダラは夜行性で、生きた個体が這っている姿を見ることはなかなかなくても、死んだ個体なら日中に見ることもよくあります。道路でつぶれていたり側溝に落ちて干からびていることもある(悲しいですが)ので、チェックしましょう。
しかしシロマダラは個体数も少なく分布も局所的、地域によっては絶滅危惧種に指定されていることもあるので、採集は慎重になるべきです。ただ、1匹ないしペアを持ち帰り飼育観察することは、この謎の多いヘビの生態解明に役立つことがあるかもしれません。消費的飼育ではなく、新たな知見を得る気概で飼育をすることが望まれる種です。
シロマダラの飼い方
トカゲ・ヤモリをコンスタントに入手できるかどうかがシロマダラ飼育のカギ。そこさえクリアできれば飼育は難しくはないです。餌用ヤモリが爬虫類ショップで販売しているので、入手ルートを確保しておきましょう。ネット通販だと送料も含めて結構高いです。
個体によってはピンクマウスに餌付く個体もいますが、本来の餌ではないため消化管に影響が起きるとされ、長期飼育を考えているならやめた方が良いでしょう。
エサ食いは良く、シロマダラを捕まえたその日から餌に食らいつくような個体も多いです。一方で、シロマダラは鱗の数が少なく、つまりアオダイショウのように皮膚をのびないのであまり大きな餌が食べられません。食べても吐き戻す可能性が、他のヘビに比べて高いと感じます。神経質な生活も原因かもしれないので導入直後は給餌時に振動を立てたりしないようにしましょう。温度はあまり暑いと食欲が落ち、20~25度くらいが餌付きが良いです。
シロマダラの幼蛇の画像

シロマダラは珍しい?
シロマダラを見つけると、ニュースで「幻のヘビ」として話題になりますが、夜行性で隠蔽性であるため人目に付きづらいだけです。その意味では、普通の人(夜の自然フィールドに出歩かない人)にとっては珍しいかもしれません。
個体数も、普通種のアオダイショウやシマヘビなどに比べたら少ないようですが、それは種の元々の特性で、他のヘビや他の爬虫類と比べて特に絶滅が心配されている、などのようなことはありません。
シロマダラを見つけたらどうする?
私は、環境系組織という仕事柄、「シロマダラを見つけたら、どうすればいいのか」などと聞かれることがよくあります。
回答はズバリ「自然にいる生き物なので、特に何もしなくていい」です。
しかし、なぜこのようなことを頻繁に聞かれるのか不思議に思っており、ある時、この手の質問を聞いてきた意図を、そのご本人に聞いてみると、
「珍しい生き物は保護すべきだと思うから、シロマダラを見つけたらどうすればいいか聞いた」
とのこと。
「保護」という言葉が、「希少生物を保護する」的な意味と、「犬や猫を保護する」的な意味とでごっちゃになっているのでは?と感じました。しかし、それと同時に「実はこれ、もしかしたら割と一般的な感覚なのかもしれない」とも思いました。
希少生物を「保護」をするということは「生息環境を含めて、自然の状態であることを維持する」ことであり、個体を捕まえて、その個体の生存を確保することとイコールではないのです(しかしながら、例えば、絶滅種のニホンカワウソやニホンオオカミ等が発見された場合であれば、話は別ですが)。
犬猫を「保護」するということは、例えば人間の子供を「保護」するのと同じことで、その個体(個人)の生命や健康を守るということです。
同じ「保護」でも、意味合いが全く異なるのです。
再度結論を申しますと、もしシロマダラを見つけたら、特に何もしなくて良いです。
強いていえば、シロマダラの生態からして、ヘビオタクではない普通の人はなかなかお目にかかれないヘビであることは事実ですから、記念に写真や動画でも撮っておくのは良いかもしれませんね。









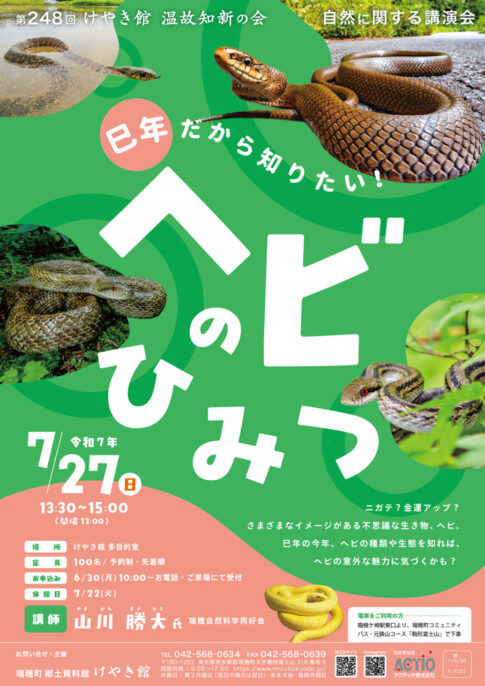
[…] 参考サイト○Wikipediahttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%80%E3%83%A9○生物モラトリアムhttps://namamono-moratorium.com/shiromadara-poison-1253○山川自然研究所https://jnol.jp/siromadara/ […]
[…] 画像の出典 […]